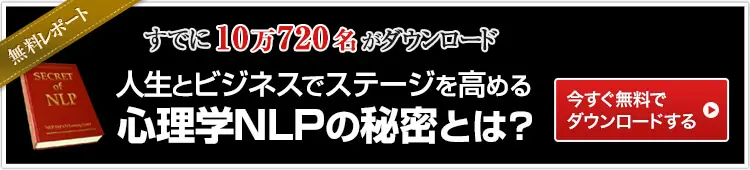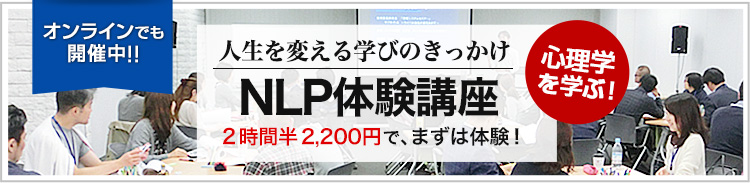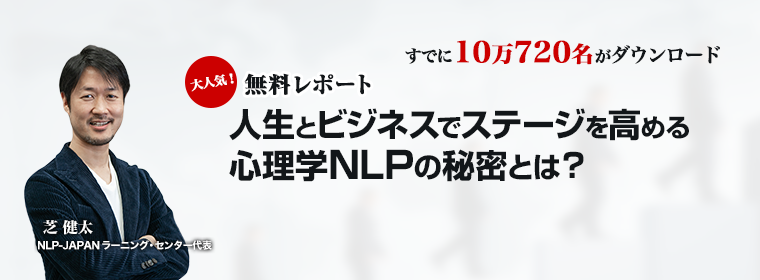- 周囲と比べて落ち込んでしまう。
- 何か嫌なことがあると、
自分のすべてを否定したくなってしまう。 - 「こんな自分が何か意見を言っても
迷惑なのでは」と思ってしまう。
日常でこのように考えてしまう人は、
自尊心が低くなっている可能性があります。
なかなか自分に自信が持てないというのは、
とても苦しいことです。
この記事では、自尊心を高める方法を
心理学NLPの視点からお伝えしていきます。
自尊心の低い状態から抜け出し、
仕事や人生を変化させたいとお考えの方は、
ぜひ最後までご覧いただければと思います。
目次
1.自尊心とは

自尊心とは、自分の心を尊重することです。
自分という存在を尊重し、肯定的に捉えることで、思考や行動が常にポジティブにある心の状態、態度のことを言います。
また、辞書によると自分の人格を大切にする気持ち。
また、
自分の思想や言動にも自信を持ち、他からの干渉を排除する態度。プライド。
(小学館『大辞泉』より)
とあります。
しかし、現在よく使われる自尊心は、心理学的な自尊心(Self-esteem)の意味合いが大きく、そこには他人からの干渉を排除するや、プライドという意味合いは含みません。
なぜなら、自分という存在に対して肯定的であると、他人からの干渉さえも肯定的に捉え、柔軟に対応できるからです。
プライドは理想の自分や他人と比較したときに生まれやすいものであり、何かと比較し、優越感や劣等感を感じることは、自分の存在そのものを肯定的に捉えている状態とは言えません。
また、NLP心理学では、自分のことをどのように捉えているかというセルフイメージと自尊心は密接な関係にあるとお伝えしています。
セルフイメージは人間関係や収入など、人生全般に影響していると言われています。
そして、自尊心が低い原因の1つには、セルフイメージが関係していると考えられるのです。
2.自尊心が高い人の特徴

この章では、自尊心が高い人の特徴をお伝えしていきます。
皆さんの周りにいる、自尊心が高そうな人を思い出して頂きながら読み進めていくと、より実感が湧いてくると思います。
2-1.自分の間違いを認められる
自尊心が高い人は、自分の間違いや失敗を素直に認められます。
自分への肯定感が高いため、自分の間違いや失敗を素直に受け止めることができます。
そして間違いを認め、相手に謝罪したり次に活かそうとします。
そのため、さらに自分への肯定感が増していき、自尊心が高まるというプラスのサイクルが生まれるのです。
2-2.ブレない軸がある
自尊心が高い人は、ぶれない自分軸を持っています。
自分を常に肯定的に捉えているので、自分の考えや思いを尊重できます。
また、周りの意見に流されたり、困難な状況でもネガティブにならず、自分を信じることができるのです。
2-3.肯定的な言葉を使う
自尊心が高い人は、表情が常に明るく、笑顔でポジティブな肯定的な言葉を使います。
「それは、無理」や「してくれない」、「△△できない」ではなく、「◯◯する」や「◯◯したい」、「◯◯できる」と言った言葉を使います。
このような肯定的な言葉は、知らず知らずのうちに無意識に刷り込まれていくので、自分をさらに肯定的に捉えるようになるのです。
2-4.切り替えが早い
自尊心が高い人は、切り替えが早いという特徴があります。
たとえネガティブな出来事があっても、肯定的に捉えることができるため、「この経験を次に活かすぞ」や「これは悩んでもしょうがない」と、すぐに気持ちを切り替え、次に進むことができるのです。
2-5.チャレンジ精神がある
自尊心が高い人は、チャレンジ精神があります。
失敗することよりも、チャレンジすることに価値を見出します。
例え失敗しても長期に渡ってクヨクヨしたりせず、失敗体験を学びに変えて成功するまで諦めずにチャレンジしていくのです。
2-6.感謝の言葉を口にする
自尊心が高い人は、「ありがとう」と言った、感謝の言葉をよく口にします。
自分を大切にし、周囲の人も尊重し大切にします。
そして、自分に対して何かしてくれる時はもちろん、一緒に仕事をしたり、一緒にいてくれることそのものを幸せと感じ、感謝の気持ちとともに「ありがとう」という言葉で相手に届けるのです。
3.自尊心が低い人の特徴

この章では、自尊心が低い人の特徴をお伝えしていきます。
自尊心が低い人の特徴は、一言でいうとネガティブ思考になってしまいがちということです。
また、自尊心が低くなっている原因は5章で詳しくお伝えしますが、幼い時のネガティブな体験が原因となり、今でも苦しんでいるということが起こるのです。
もちろん、自尊心が高い人でも、ネガティブな思考や感情を一切持たない人はいません。
ただし、以下のようなネガティブな思考や感情を長い間、常に感じている場合、自尊心が低くなっている可能性がありますので、詳しく見ていきましょう。
3-1.人と比べて落ち込んだり、嫉妬したりする
自尊心が低い人は、人と比べて自分が劣っていると感じると落ち込んだり、嫉妬を感じてしまう傾向があります。
また、自分が優れていると感じると優越感に浸ったり、人を見下すような態度で接してしまうということが起こったりします。
これらはすべて自分を肯定的に捉えられていないために、人と比べることで自分の存在価値をはかろうとしてしまうことから起こることなのです。
3-2.過去の失敗にとらわれる
自尊心が低い人は、過去の失敗にとらわれてしまって抜け出せないことがあります。
かなり昔のことなのに常に失敗を口にして、クヨクヨしてしまいます。
また、まったく違う分野の話なのに、失敗するのが怖く新しいことにチャレンジすることができず、避けてしまいます。
3-3.自分を否定する
自尊心が低い人は、何かと自分を否定してしまいます。
常に悪いところにフォーカスし、たとえ何かがうまくいったとしても良くないところを見つけ出し、
「自分はダメだ。価値がない」と、
すべてを否定してしまいたくなるのです。
人から褒められても素直に受け取れなかったり、「何か裏があるじゃないか。そうでなければ自分を褒めるなんてありえない。」と考えたりします。
3-4.周囲に流されやすい
自尊心が低い人は、周囲や人に流されやすいという特徴があります。
自分のことを肯定的に捉えられないので、自分の意見がなかったり、あったとしても自分を尊重できずに人の意見を優先したり、従ってしまうのです。
3-5.諦めが早い
自尊心が低い人は、諦めるのが早いという特徴があります。ちょっとうまくいかないことがあると「やっぱり自分には無理」と思い込み、諦めてしまうのです。
これは本人も気づいていない心の奥底で「早い段階で諦めることで、大きな失敗をさけることができる。」と思っていたりするのです。
なぜなら諦めることで、今以上に自分を否定したり、傷つけように心を守ろうとしてるからです。
4.自尊心が低い原因

この章では、自尊心が低い原因についてお伝えしていきます。
一般的に言って、自尊心が低い原因は幼いころのネガティブな体験が大きな原因だとお伝えしました。
そして心理学NLPでは、そこにセルフイメージの低さが大きく関連していると考えられています。
4-1.過去の失敗体験
自尊心が低い原因の1つは、過去の失敗体験が関係しています。
例えば小学生の時、人前で発表した際に言い間違いをしてしまい、みんなから大笑いされたという体験があったとします。
もともとは緊張も特にしていなかったのに、たった1回の言い間違いで、それ以来、人前で話そうとすると緊張で汗が止まらなくなってしまい、
「自分は人前で少しも話すことはできない。なんてダメなんだ。」と自分を肯定的に捉えられなくなってしまうのです。
4-2.周囲からの叱責や批判
自尊心が低い原因の1つは、周囲からの批判や叱責が関係しています。
例えば、幼いころ親や学校の先生から繰り返し怒られたりすることで「自分はダメな人間なんだ」と思い込んでしまうことがあります。
本来であれば「その人の存在」と「間違った叱られるべき行動」は分けて考えることが大切ですが、言葉として「〇〇は本当にダメね」と言われてしまい、自分の存在価値そのものが下がってしまうのです。
他にも、いじめや同学年の生徒から批判されることにより「自分はダメな人間なんだ。価値がないんだ。」と思い込んでしまうことが起こるのです。
4-3.幼少期からの成功体験がない(と思い込んでいる)
自尊心が低い原因の1つは、幼いころからの成功体験が少ないとうことがあげられます。
例えば、常にお兄ちゃんと比べられ、「どんなに頑張っても、何をやってもお兄ちゃんに勝てない。両親からの愛は貰えない。」と絶望感に近い感情を持ってしまう場合があります。
他にも、学校のテストやスポーツの大会で頑張っていい成績を残しても、褒めて貰えるどころかダメだった所ばかりを指摘され、成功したという感覚や、達成感が持てなくなってしまうということも起こるのです。
4-4.幼少期に決定権がなかった
自尊心が低い1つの原因は、幼いころから決定権が一切なかったということがあげられます。
例えば、進学先や両親の離婚でどちらの親についていくかといった、人生での大きな選択や、それこそ服を買うといった日常の選択までをすべて親が決めてしまったということに起こります。
このように自分に決定権がなかった場合、幼い時は自分の意思を示したとしても、
「あんたは子供だから」と意思を繰り返し否定されたり、無視されることで、決めることそのものを諦めてしまっていることがあるのです。
5.自尊心を高める方法

この章では、日常で行える自尊心を高める方法をお伝えしていきます。
このようなことに初めて取り組む方へのアドバイスをさせていただくと、初めから完璧を求めないことです。
毎日行うのを基本としつつも、週に4日、5日できたらOKという具合です。
まずはハードルを低く設定し、小さい成功体験を積み重ねていくことが大切です。
まずは1か月間やってみたいと思えるものを行い、その後さらに2か月程度、継続することをお勧めします。
5-1.感情日記をつけ、客観的に眺める
自尊心を高めるためにお勧めなのは「感情日記」をつけて、客観的に眺めてみることです。
自分が感じているネガティブな感情を客観的に捉えられるようになることで、
- ネガティブな感情に振り回されない自分
- ネガティブな感情に代わる、
人生が良くなるための考え方や行動
これらが手に入りやすくなるのです。
実際に日記をいきなりつけろと言われても、何を書いたらいいか分からず、難しいかもしれません。
このようなときは、テーマを決めて日記をつけることをお勧めしています。
その1つとして、1日の中で感情を感じた瞬間を思い出し、その時のことを書くという方法です。
ポイントは、ポジティブな感情もネガティブな感情もすべて書いてみるということです。
<やり方の例>
- 1日の中で感情を感じた瞬間を思い出し、紙やスマホ、パソコンに書き出す(お勧めは紙のノート)
- ノートを半分に折って左にネガティブな感情のテーマとその詳細。右にポジティブな感情のテーマとその詳細を書く。
- ネガティブな項目について、自分が大切に思っている、友人や家族が感じていることだとしたら、どのように客観的にアドバイスをするかを考える。
【例】
|
<怒り> コンビニで並んでいる列に割り込まれた。 |
<嬉しさ> 自動販売機で数年ぶりにもう1本当たった。 |
以上です。
最初は感情がなかなか思い出せなかったり、ポジティブに考えられなくても問題ありません。
1日の振り返りが習慣化してくると、感情を思い出しやすくなったり、日常で自分の感じている感情を客観的に捉えられるようになるのです。
5-2.感謝日記を付ける
こちらは「感謝」をテーマに日記をつけるというやり方です。
1日を振り返り、
- 人からしてもらったこと
- ラッキーだったこと
- ありがたいと感じること
など、箇条書きで書き出していきます。
普段ネガティブな思考や場面に向いていた意識が少しづつ感謝というポジティブなものに意識が向くようになります。
そして、自分の中の世界観が変わっていくのを感じるようになります。
書き出すポイントは、どんな小さなことでもいいので、書き出していくことです。
【例】
- 落ちたペンを拾って貰った
- いつも買うパンが50円引きで売っていた
- 仕事は大変だけど、こうしてお休みは
趣味のゲームができるのは嬉しい - こんな可愛い子供を産んでくれて
ありがとう
など
このように感謝日記をつけることで、自分の世界観がポジティブになっていくと、おのずと自分への肯定感が上がり、自尊心も高まっていくのです。
5-3.自分で決断する機会を増やす
こちらは、日常何気なくやっていることを意識して決断していくというやり方です。
この機会を増やすことで、実は自分で決断できることが思った以上に多いことに気づくようになります。
大切なポイントは、「自分が決断できることから始める」ということです。
- 朝ごはんに何を食べるのか
- そもそも食べないのか
- どんな服を着ていくのか
- どんなルートで会社に行くのか
という、ほぼ自分だけで決めれることを「自分で決めている」「自分で選択している」と感じながら日常を過ごすというものです。
そして、それがある程度意識できるようになり、「自分でこれだけのことを決めているんだ」という実感が湧いてきたら、次に仕事や家庭等、人との関わりの中で少しづつ自分の意思を伝えたり、決断していきます。
最初はうまく伝えられなかったり、自分の意見と違う意見が採用されることがあるかと思いますが、まずは意思を伝えることを行っていきます。
そして重要なことは、「自分が決められること」と「そうではないこと」をしっかりと分けて考えるということです。
今、自分が決められることに集中することで、決断力がついていきます。
そして長期的には仕事での役割が上がったりすることで決められる範囲が広がり、自分の存在価値をより感じることが増え、自尊心も高まっていくのです。
5-4.as if フレームを使う
NLPでお伝えする中に、「as if フレーム」というものがあります。
これは、自分にとって制限や壁と感じることを「もし~だとしたら」と、変換して口にすることで、可能性を広げる言葉の使い方になります。
例えば、「私には無理、できない」と思ったとき、「もし、やってみるとしたら?もし、できたとしたら?」と変換していきます。
これは、私たちの脳の機能を活用した質問であり、私たちの脳は質問を投げかけられれると自動的に答えを探そうという機能を持っています。
例えば、「昨日の夜何を食べた?」と聞かれ、「テレビドラマを見た」と答える人はいません。
質問に対して、脳が勝手に検索をはじめ、「カレーを食べた」や「何も食べていない」と答えるのです。
この機能を使い、「私には無理、できない」と思ったとき、
- もし、やったとしたら?
- もし、できたとしたら?
と自分に質問することで、思考がまわりネガティブから抜け出しやすくなるのです。
他にも、
- もし、私にいいところがあるとしたら?
- もし、私が意見を言えるとしたら?
など、口にすることで今までとは違う発想が生まれてくる可能性があるやり方です。
5-5.リフレーミングする
NLPでお伝えする中でも、とても人気があるテーマの1つがこのリフレーミングです。
リフレーミングは、リ(再び)・フレーム(枠)ということで、「物事の捉え方、枠組みを再度変える」という意味になります。
リフレーミングすることで、自分にとってマイナスと思えていることを違った視点で捉えることで、プラスの意味に変えていくことができるのです。
例えば、「私、消極的なんです」という意味をリフレーミングすると「物事を深く考える人なんですね」と言い変えることができます。
また、「私、人に流されやすいんです」は「周囲の人に気配れる人なんですね」と意味づけを言い変えることができます。
他にも、「諦めが早い」を「好奇心旺盛」と捉え方を換えることもできます。
長所と短所は表裏一体と言われることがあります。
まさにそれを意識的に捉え方を変化させていく方法がこのリフレーミングです。
心理学NLPではこのリフレーミングを14パターン学ぶことができ、日常で使うことで自分だけではなく、周囲の人の自尊心を高めることができるスキルとして人気があります。
6.それでも自尊心が高まらない場合には...

6章の方法を継続し、習慣化していくと少しずつ自尊心に変化が起きていくのを感じられるでしょう。
それでも、なかなか変化が感じられない場合は、もっと根本の要因に目を向けていく必要があります。
特に5章でお伝えしたような、過去の幼い時のネガティブな体験が大きく影響している場合、それが変化の足枷となっているかもしれません。
その足枷を取り外すアプローチを行うことで、低くなっているセルフイメージを根本から変えることができるのです。
そうして内面を改善することで自尊心が短期間で大きく高まるのです。
私たちがお伝えしている心理学NLPは、別名「脳と心の取り扱い説明書」とも呼ばれており、途中でご紹介したスキル以外にも、
セルフイメージを変化させ自尊心を高める学び・アプローチがたくさんあります。
また、自尊心を高める以外にも、
- 目標達成、問題解決の能力を高めること
- コミュニケーション能力を
飛躍的に向上させること - 心の傷やマイナス面を解消すること など
人生をより良くするために必要なことを、バランスよく学ぶことができます。
NLPについてご興味を持たれた方は、すでに10万名以上の方がダウンロードされた「NLP無料レポート」をぜひご覧ください。
↓
人生とビジネスでステージを高める心理学NLPの秘密
2時間半の気軽な体験講座も、各地で行っています。
↓
NLP体験講座(東京・名古屋・大阪・福岡・オンラインで開催中)
さらに、NLPの基礎を習得する10日間コースにご興味がありましたら、こちらをご覧ください。
↓
NLPプラクティショナー認定コース
まとめ
自尊心とは、自分という存在を肯定的に捉え、思考や行動が常にポジティブにある心の状態、態度のことでした。
自尊心が低くなっているとしたらそれは、幼少期のネガティブな体験が大きく影響している可能性が大きいのです。
もし自尊心を本気で高めたい変えたいと思ったら、過去の自分の内面と向きあうような心理的アプローチが必要なのです。
この記事では、その具体的な方法もお伝えしてきました。
この記事が、皆さんの低い自尊心を大きく変化させるお役に立てれば嬉しく思います。