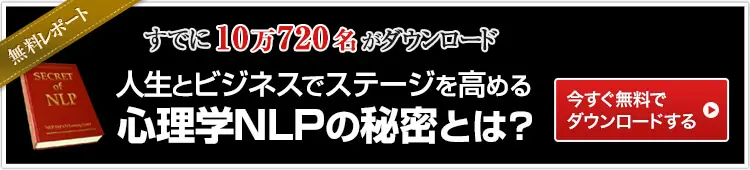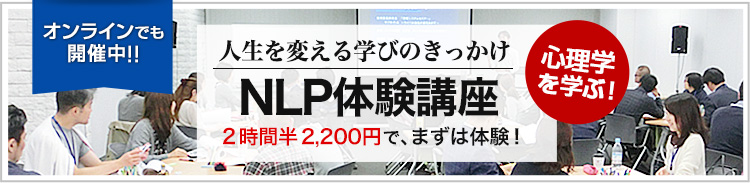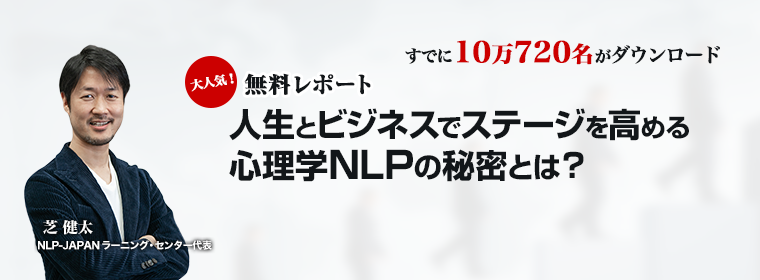著:アンドリュー・T・オースティン
「MoM
(メタファー・オブ・ムーブメント)」とは、
メタファーを通じて
人の深層心理を分析し、
本人さえ気づいていない
心理状態を読み解くメソッドです。
そのため、
『悩みの"本質"を見抜いてしまう術』
このようにも言われています。
普段、人が何気なく使っている
メタファーに隠された
意味を理解することで、
自分や他人の本質や抱えている
問題を見抜き、
深い気づきを得ることができます。
自己や他者理解に役立ち、
特にコーチやセラピストなど、
人の成長と問題解決を
支援する方にとって
強力な武器となります。
MoMでは数十種類に分類された
メタファーそれぞれが、
その人が直面している問題の状態を
明確に表していると考えます。
あなたもMoMを学び、
様々なメタファーを知れば
深層心理のディープな世界に、
どっぷりとハマるかもしれません。
MoM事例:お金の緊張を打ち負かす

Kさんからの質問です。
「頭の周りに大きな輪ゴムが巻き付いていて、それが財布につながっています。
さらに、この大きな輪ゴムは私の心臓を通過して財布につながっています。
財布を開いてお金を使うことが、なぜ苦痛なのかがわかりました。
これは、痛みと固着のメタファーではないでしょうか...
そして身体を貫通しています。アドバイスをください。」
このメタファーにはいくつかの興味深い特徴がありますが、まずは、いつものように慣用句から。
- ここには緊張が満ちている
- 財布を開くのは緊張を伴う
- お金を使うと気が張り詰める
- この緊張感は心を打つ
緊張を意味するTension(テンション)には、張力の意味もある。
分類学の観点からこのメタファーを見てみましょう。
- 「痛み」のメタファー(人間関係):
輪ゴムが身体を貫通し、生命を脅かしている - 「重荷」のメタファー(責任):
輪ゴムは重荷のメタファーの「持ち運んでいる物」として機能し、財布もまた「持ち運んでいる物」である - 「固着」のメタファー
(ダブルバインド):
輪ゴムが固着を形成している - 「容器」のメタファー
(受け継がれたステータス):
頭に巻かれた輪ゴムは、部分的な容器となっている
表面的にはシンプルなメタファーに見えるかもしれませんが、実際は非常に複雑な状況を示しており、簡単な解決はないでしょう。
まずは、頭に巻き付いている輪ゴム、つまり「容器」の要素を見ていきましょう。
容器が示しているのは、この問題には目新しいことは何もなく、幼少期から続いていることです。
さらに、この部分的容器には伸縮性があるため、ビリーフの要素が絡んでいることもわかります。
そのため、動きに制限をかけるような容器を説明する現在のMoMプロセスは、ここでは無効だと考えます。
なぜなら、「大きくなる(成長する)」プロセスは単に緊張を高めるだけで、有益ではない可能性が高いからです。
「固着」の要素が表している最大の問題点は、財布を開くことによってダブルバインド(やっても地獄、やらなくても地獄)が起こることです。
こうした固着は、ベイトソンの6項目リストに従う傾向があります。
参考:https://en.wikipedia.org/wiki/Double_bind
ベイトソンが述べたダブルバインドを作り出すための必須要素は、コミュニケーションと家族関係に関連するものですが、
まったく同じ要素で、経済問題や法的問題、職場における問題、自然災害などの複雑な環境も説明することができます。
こうしたダブルバインドと固着のメタファーの本質は、「その場からの脱出は不可能」であることを示しています。
つまり、その人が体験していることの大部分は、セラピー的措置による変化の領域の外にあるということです。
多くの心理療法で共通して行われる体感覚的否認の創出は、それが成功してしまうとすれば、逆に大きな問題となるでしょう。
しかし、実際の治療においては、こうした変化を生み出すのに効果的なはずのテクニックが失敗する可能性のほうが高く、
クライアントはセラピストが状況の本質を理解していないことに気づきます。
そしてセラピストは、クライアントが変化することに抵抗する、難しいクライアントであると感じるでしょう。
最も明白なのが、このメタファーの「重荷」の側面です。
結局のところ、セラピーの実践者側から見れば、意図するアウトカム 対 適用した手法の問題となるでしょう。
重荷のメタファーでは、その重荷をどこに持って行こうとしているのかを探究し、方向、距離、移動手段、移動速度を探る必要があります。
固着の場合、「その場からの脱出は不可能」でありながらも、この特定の固着は簡単に携帯することが可能であることを思い出してください。
ここから何が推測されるかは、読者の皆さんの判断にお任せします。
しかし、最も重要な手がかりとなる「痛み」の要素(つまり、身体を貫通)がここにはあります。
「痛み」のメタファーとは、通常、私たちが他者と築く人間関係の本質や、自分の立場などと関連しています。
また「痛み」は、繰り返されるスキーマ、つまり、特定の人間関係において繰り返されている、問題となるパターンが存在していることを示唆しています。
そして、その人間関係の本質がとても心に近いものであることも示しています。
そこには鼓動があり、脈打ち、リズムがあります。(注:お金にはそうした鼓動はなく、液体のように流れる性質があります)
しかし、打ち負かせるものはあります。人もそう、問題もそうです。
問題は、これが最善の方法かどうかということです。おそらくそうではありません。
犬を打っても良い犬になるわけではありませんし、問題がなくなるわけでもありません。
問題を打って負かせても同じことです。そこには同じ構造があります。その結果は、犬と大差ないのです。
この問題を打ち直すことはできるのでしょうか?おそらくできるでしょう。
しかし、それが役に立つのかということです。
アンドリュー・T・オースティン氏から日本で直接学べる講座はこちら
NLPトレーナー アンドリュー・T・オースティン (Andrew T.Austin) プロフィール
著者より許可をいただき掲載しています。
https://metaphorsofmovement.co.uk/beating-money-tensions/
All Rights Reserved (C) 2024 Andrew T. Austin and The Fresh Brain Company Ltd